小学校受験では、知識・常識分野の中でも“季節感”が頻出。
「春の花は?」「秋の食べ物は?」「夏の行事は?」など、
身近な自然や文化をどれだけ“自分の言葉で理解しているか”が問われます。
暗記だけで覚えることもできますが、実体験を通して理解する方が圧倒的に定着します。
🕊️ 学習を始める時期は「お受験を決めた日」から!
多くの家庭では「年長になってから」と考えがちですが、
実は季節の学習は早ければ早いほど有利です。
なぜなら——
年中の秋から学習を始めた場合、入試までに四季をたった1回ずつしか経験できないから。
季節ごとの花・食べ物・行事を3か月で網羅するのは、かなり大変ですよね。
🌷 だからこそ、「お受験を決めたその日」から季節の学習をスタートするのがおすすめ!
🌱 家庭でできる季節感の育て方
――日常の“体験”が最強の教材!
「季節の勉強」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、実は身近な出来事の中に学びはたくさんあります。
🍱 例:4月のお花見
- シートを敷こうとしたら「シロツメクサ」が咲いていた
- お弁当には「イチゴ」が入っていた
- 「桜」を見ながら家族でランチ
この短い時間の中で、春の花・果物・行事を自然に感じ取ることができます。
deco家が特にオススメなのは”キャンプ⛺”
毎年2回はキャンプに行って自然の中で遊ぶ体験をさせています。
季節の花・昆虫・山や川の生物・星座・気象…etc
小学校受験だけでなく、小学校の理科ひいては中学受験につながる学びを実体験できるのです。
自然が大好きは息子は現在1年生ですが、3年生の理科の参考書を漫画のように読み「理科をやりたい!」と問題集を楽しんで解いています。
これも幼児期の自然とのふれあいによる興味や好奇心の賜物だと思います。
自然の中での季節の花や昆虫とふれあい+お泊りはお子さんにとって最高の学びと体験になるでしょう。
💬 声かけで“季節を意識”させる
体験をより印象に残すには、親の声かけがポイント。
「桜がきれいに咲いてるね。お花見って言うんだよ」
「これはシロツメクサ。春に咲くお花なんだよ」
「イチゴは春が旬の果物なんだよ」
子どもは興味のあるものにしか目がいかないため、
保護者が“見つけるきっかけ”を作ってあげることが大切です。
外出前にはこんな言葉がけもおすすめ👇
「今日はお花見に行くよ。今は4月だから“春”なんだね。桜が満開だよ!」
こうして、季節を意識させる習慣を作りましょう。
🎓 学校が“季節問題”で見ていること
小学校の先生たちがこの分野を重視する理由は、
「自然や文化を感じ取れる感受性豊かな子ども」を求めているからです。
ペーパーで問われるのは知識の確認ですが、
その背景には「経験しているか」「言葉で説明できるか」という狙いがあります。
🧩 忙しい家庭でもできる!遊びながら学べる教材
とはいえ、すべての季節行事や植物を体験するのは難しいですよね。
そんな時に頼れるのが、“お風呂ポスター”や“季節カード”です。
🔸 deco家おすすめアイテム
- 🛁 お風呂の学校シリーズ(季節の花・食べ物・行事・二十四節気などを網羅)
→ 防水タイプで毎日視覚に入るから、自然と記憶に定着! - 🃏 季節カード90枚セット
→ フラッシュカード形式で、親子でクイズ感覚に。ゲームっぽく学べるから飽きません。
「遊びながら覚える」ことが、結果的に一番の近道です。
🛒楽天でチェック:お風呂ポスター3枚セット
🛒楽天でチェック:季節カード90枚セット
🌸 まとめ:体験+声かけ+遊びが季節学習の3本柱
小学校受験の「季節」問題は、知識だけでなく心の豊かさを表現できるチャンス。
家庭の中で四季を感じ、親子の会話から自然に学びを広げていきましょう
関連記事
- 頑張りすぎない受験サポート|共働き家庭でも子どもを伸ばす親の習慣
- 小学校受験にかかる費用はどのくらい?知っておきたい全費用と節約ポイント
- 【2025年版】働くママでもできる!小学校受験に強い通信教材6選|家庭で合格力を育てる
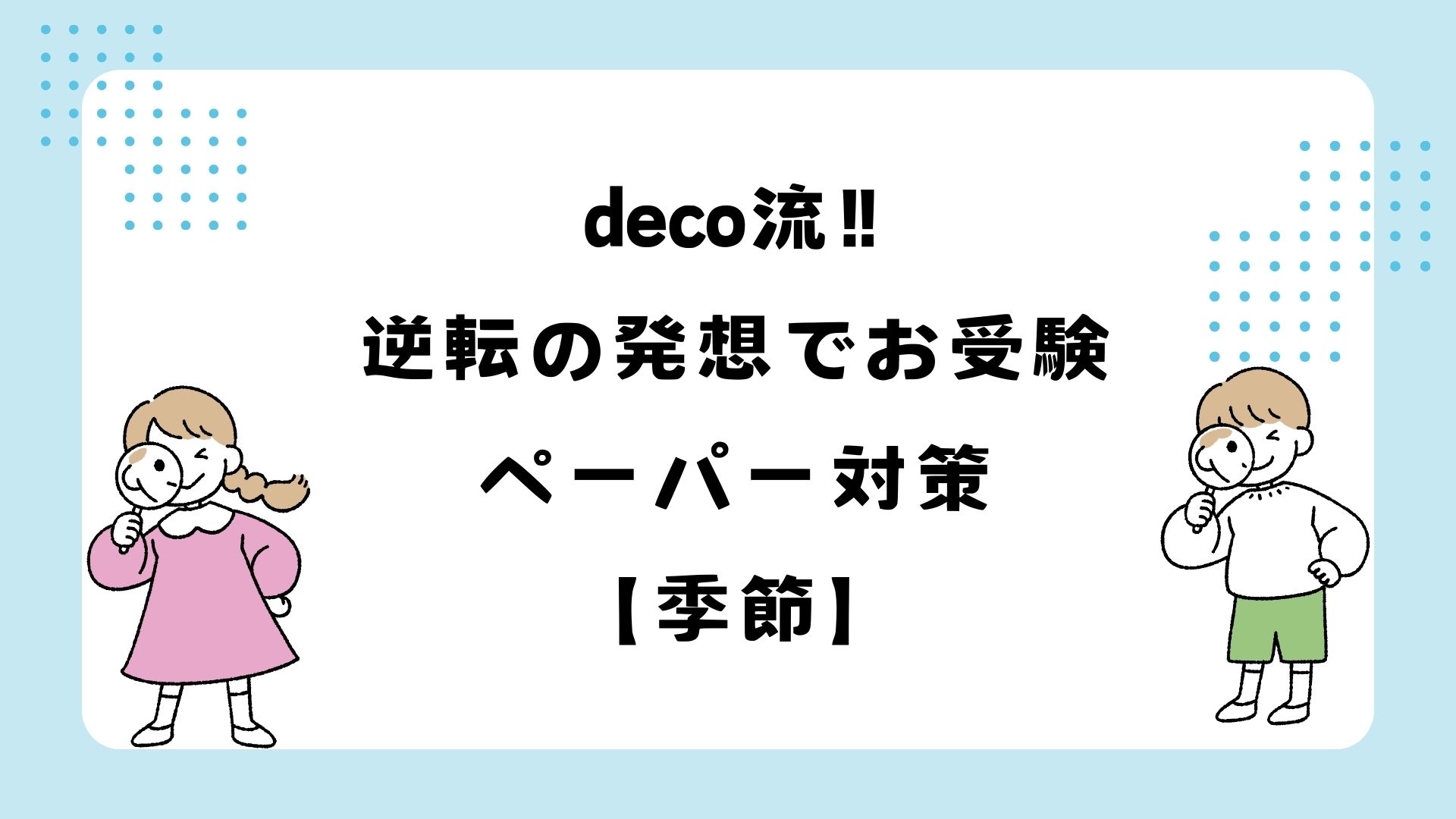
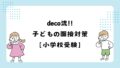
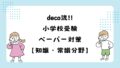
コメント