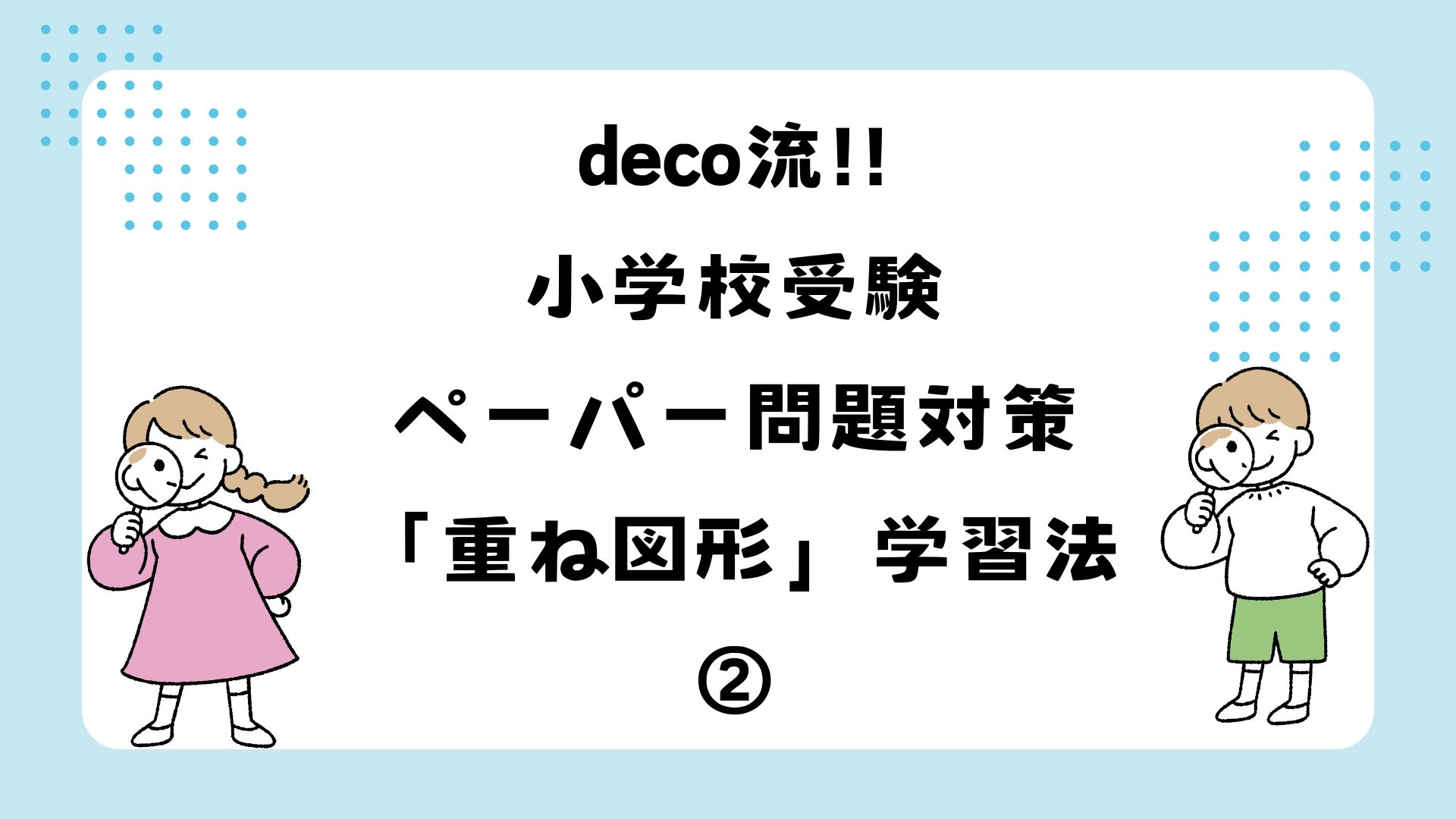
この記事にはアフィリエイト広告が含まれます
☑この記事でわかること
- 小学校受験で折り重ね図形が頻出する理由
- 基本的な出題パターンと例題
- 折り重ね図形を解くための考え方とステップ
- 家庭でできる練習法と声かけのコツ
- 遊びながら図形感覚を育てる知育教材の紹介
- オススメ問題集(▶ ジュニアウォッチャー/ひとりでとっくん)
折り重ね図形とは?「小学校受験3大苦手分野」のひとつ
小学校受験のペーパーで多くの子が苦手とするのが、
回転図形・鏡図形・折り重ね図形の3分野。
折り重ね図形は、
「左右に図が描かれた長方形を真ん中の線で折ったらどう重なるか?」
を考える問題です。
②がその折り重ね図形にあたります。
一見シンプルに見えて、空間認識力・反転イメージ力の両方が求められます。
苦手なお子さんが多いぶん、得点差をつけやすい分野でもあります。
なぜ折り重ね図形が頻出なの?
小学校受験では、
単に暗記ではなく「自分で考える力」=思考力・空間認識力が問われます。
この力は、入学後の算数や図工、プログラミング教育にも直結。
だからこそ、受験でも毎年必ず出題されるのです。
折り重ね図形の出題パターン
よく出るタイプはこの3つ👇
1️⃣ 線図形の反転
→ 直線や曲線の反転位置を考える問題
2️⃣ 色マス図形の反転
→ 4×4や5×5のマスに色が塗られており、折ると重なる位置を答える
3️⃣ 点つなぎの反転
→ 点つなぎで描かれた図が、折り返すとどんな形になるかを推測
→実際に点をつないで図形を書き解答することが多い
折り重ね図形を解くステップ
STEP①|まずは「鏡図形」を理解しよう
折り重ね図形は“鏡映像”の応用です。
鏡図形が苦手なままだと、折り重ね図形も混乱しがち。
▶ 先にこちらを復習!
【保存版】鏡図形の完全攻略ガイド|家庭でできる練習法
STEP②|「どちらが動く紙か」を見極める
問題には多くの場合、折る方向を示す矢印があります。
→ 矢印の向きを見て、どちら側の図形が反転するかを判断しましょう。
STEP③|線ではなく「点の移動」で考える
折り重ね図形は「線を追う」よりも「点を追う」方が正確です。
たとえば、線の”始まり(起点)と終わり(終点)”を見つけて、
それぞれが折り目を中心にどこへ移動するかを考えます。
📍起点と終点を移したあとに、その2点を線で結ぶ——
それが正しい反転図です。
家庭でできる!折り重ね図形トレーニング
おうち学習でおすすめなのは、声かけ+手を動かす練習。
- 「この点はどこに移動すると思う?」
- 「下の線のまんなか?それとも右の角?」
と問いかけながら、お子さん自身に説明させるのがコツです。
自分の言葉で説明できれば、理解は一気に深まります。
おすすめ教材・知育玩具
🧩 思考力を育てる七田式「重ね図形パズル」
遊びながら「重ね」を学べる知育パズルもおすすめです。
人気の「七田式・重ね図形パズル」は、
“重ねる・回す・反転する”の3大苦手分野を一度に練習できます。
お子さまがゲーム感覚で取り組めるので、
「苦手」を「楽しい!」に変えるきっかけになります✨
🔗 楽天市場で見る(七田式 重ね図形パズル)
🔗Yahoo!ショッピングで見る
遊びながら“反転”を体感できる知育教材。
手で折る → 目で確認 → 予測力が育つ!
問題演習で定着させよう!おすすめ問題集
「解き方がわかっても、数をこなさないと定着しません」
基礎から応用まで段階的に練習できる教材を選びましょう。
📘 ジュニアウォッチャーシリーズ(重ね図形)🔗 ジュニアウォッチャー
📗 ひとりでとっくん47 重ね図形🔗ひとりでとっくん
どちらも単元別・レベル別に構成されており、
苦手克服にもぴったりです。
まとめ|折り重ね図形を制す者が受験を制す!
折り重ね図形は、
「センス」ではなく「慣れ」と「ステップ学習」で誰でも得意になります。
家庭での取り組み次第で、
“苦手”を“得点源”に変えられる分野です。
🔑 鏡図形 → 点の移動 → 練習 → 定着
この流れを大切に、楽しみながら学習を続けましょう。
お子さまの「できた!」が自信となり、合格へ近づきます✨
関連記事
- 【保存版】小学校受験の重ね図形対策|合格する子がやっている自宅学習法とは?【学習ステップ】
- 【小学校受験】「四方からの観察」完全攻略ガイド【家庭でできる練習法】
- 【小学校受験対策】数量分野の完全攻略法|入学後も差がつく“数の構成”を家庭でマスター!
- 【小学校受験対策】関西私立・国立小 面接対策のポイント|必ず聞かれる質問30と回答例まとめ【完全版】
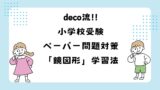


コメント