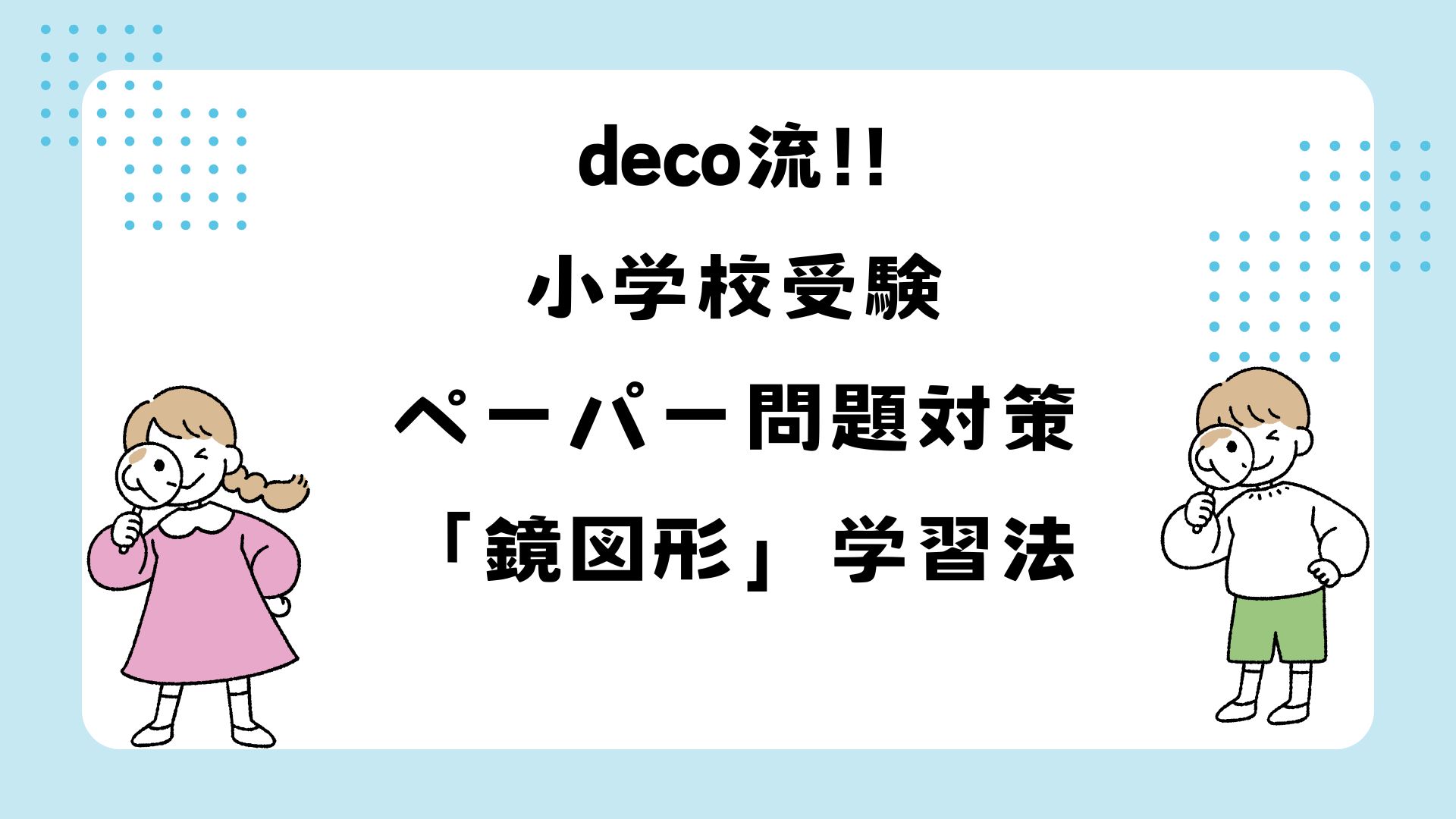
この記事にはアフィリエイト広告が含まれます
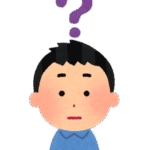
鏡に映したらどうなるの?
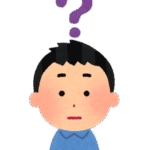
反転の方向が分からない…
小学校受験のペーパー問題で最も多くの子がつまずくのが『鏡・反転』問題です。
実は我が家も、最初につまずいたのがこの「反転」でした。
どこまで家庭で見て、どこから教室に頼るか、正直かなり迷いました。
そのときの判断や、他のご家庭が悩みやすいポイントを
実体験ベースでまとめたnoteはこちらです👇
この記事では、2児ワーママである私 deco が、実際に自宅で行ってきた
「鏡問題が得意になる家庭学習法」
をステップ別に解説します。
これを読めば、もう「鏡図形」で迷わなくなります!
鏡・反転問題はなぜ超重要なのか
小学校受験では「鏡図形」「水面に映したら」「重ね図形」「ローラーを転がすと」など、
反転の理解が必要な問題が頻出します。
実際、反転の概念があいまいなまま受験を迎えると——
- 図が少し複雑になると混乱して間違える
- 左右や上下の方向を取り違える
- 何度練習しても感覚的にピンとこない
ということがよく起こります。
でも大丈夫。
反転の考え方は、感覚ではなく「体験+手順」で身につくもの。
まずは“鏡の中では何が起こっているのか”を体験させましょう。
【ステップ1】反転とは何かを“見せて”理解させる
まずは実際の鏡を使って体験させるのが一番です。
たとえばお子さまに

右手をあげて鏡を見てみよう!
と声をかけてみてください。
「〇〇ちゃんは右手をあげているけど、鏡の中の〇〇ちゃんは左手をあげているね」
この体験が、「鏡にうつすと反対になる」という原理の出発点です。
もし左右の認識がまだ曖昧なら、
先に「右・左」や「上下」の区別を練習しておきましょう。
▼左右の認識練習はこちらもおすすめ
【ステップ2】反転する方向を見極めるコツ
鏡の位置によって反転の方向は変わります。
たとえば下のような図を想像してみましょう。
この2つでは反転の向きがまったく異なります。
deco家ではこのとき、
「鏡の方向にぱったん」
という言葉で教えていました。
鏡がある方向に向かって絵をぱったん!と折るイメージ
こうすると、鏡の左右位置だけでなく上下反転(水面反射)にも対応できるようになります。
ポイントは「鏡の位置がどちらか」をまず確認すること。
これだけでケアレスミスがぐっと減ります。
【ステップ3】複雑な図は「細分化」して考える
鏡問題を苦手とする子の多くは、
全体を一気に反転させようとして混乱するタイプです。
そんなときは、絵を小さなパーツに分けて考えましょう。
例①:🐄 牛の絵
→「牛の顔の向き(右)」と「足の位置(下)」に分けて反転を考える。
質問例:
「牛は今右を向いているね。鏡にぱったんしたらどっちを向くかな?」
「足は下にあるね。鏡の方向にぱったんしたらどこにいくかな?」
例②:図形
→「中央の山のような形(右)」と「三角(右上と左下)」に分けて反転を考える。
→図形を他のものに見立てたり一部分ずつ注目して考えると分かりやすい。
質問例:
「真ん中にあるお山の形の頂上は右にあるね。鏡にぱったんしたらどっちを向くかな?」
「右上に三角があるね。鏡の方向にぱったんしたらどこにいくかな?」
「左下に三角があるね。鏡の方向にぱったんしたらどこにいくかな?」
このように部分ごとに確認→全体を再構成することで、
難しい問題も確実に解けるようになります。
こうしたペーパー対策を進める中で、
「これって願書や面接ではどう評価されるんだろう?」
と感じたことはありませんか?
我が家は、家庭学習・教室・願書・面接を
バラバラに考えて遠回りしてしまいました。
同じ失敗をしてほしくなくて、
受験全体をどうつなげて考えたかをnoteにまとめています。
苦手克服におすすめの教材3選
お子さまのレベルに応じて、無理なく段階的に練習できる教材を選びましょう。
| 教材名 | 特徴 | リンク |
|---|---|---|
| ひとりでとっくん81 鏡映像 | 初心者でも取り組みやすく、反転の基本理解に最適 | Amazonで見る |
| ジュニア・ウォッチャー鏡図形 | 本番の出題形式に近く、実戦練習ができる | 楽天市場で見る |
| こぐま会教材 もこもこゼミ | 重ね図形・鏡映像など幅広い分野の教材が毎月届く | モコモコゼミ |
✨アドバイス:
苦手克服には「簡単→標準→応用」の順にレベルアップするのがポイントです。
最初から難問に取り組むより、成功体験を積む方が伸びが早くなります。
※家庭学習を続ける中で、
「このやり方で合っているのか」
「教室は今のままでいいのか」
と不安になる方も多いと思います。
私自身が小学校受験を完走して感じた
✔ やってよかったこと
✔ 遠回りだったこと
✔ もっと早く知りたかった判断軸
をnoteにまとめています。
まとめ:家庭での小さな積み重ねが合格につながる
鏡図形・反転問題を得意にするには次の2つが鉄則です。
- 鏡の位置を意識して「鏡の方向にぱったん」
- 図を細分化して、部分ごとに反転を確認する
この2つのコツさえつかめば、
どんな問題でも落ち着いて解けるようになります。
反転の考え方は、小学校受験だけでなく、
図形感覚・空間認識力を養う土台にもなります。
焦らず、楽しく、お子さまのペースで進めていきましょう🌸
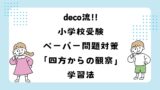
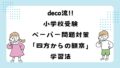
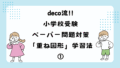
コメント