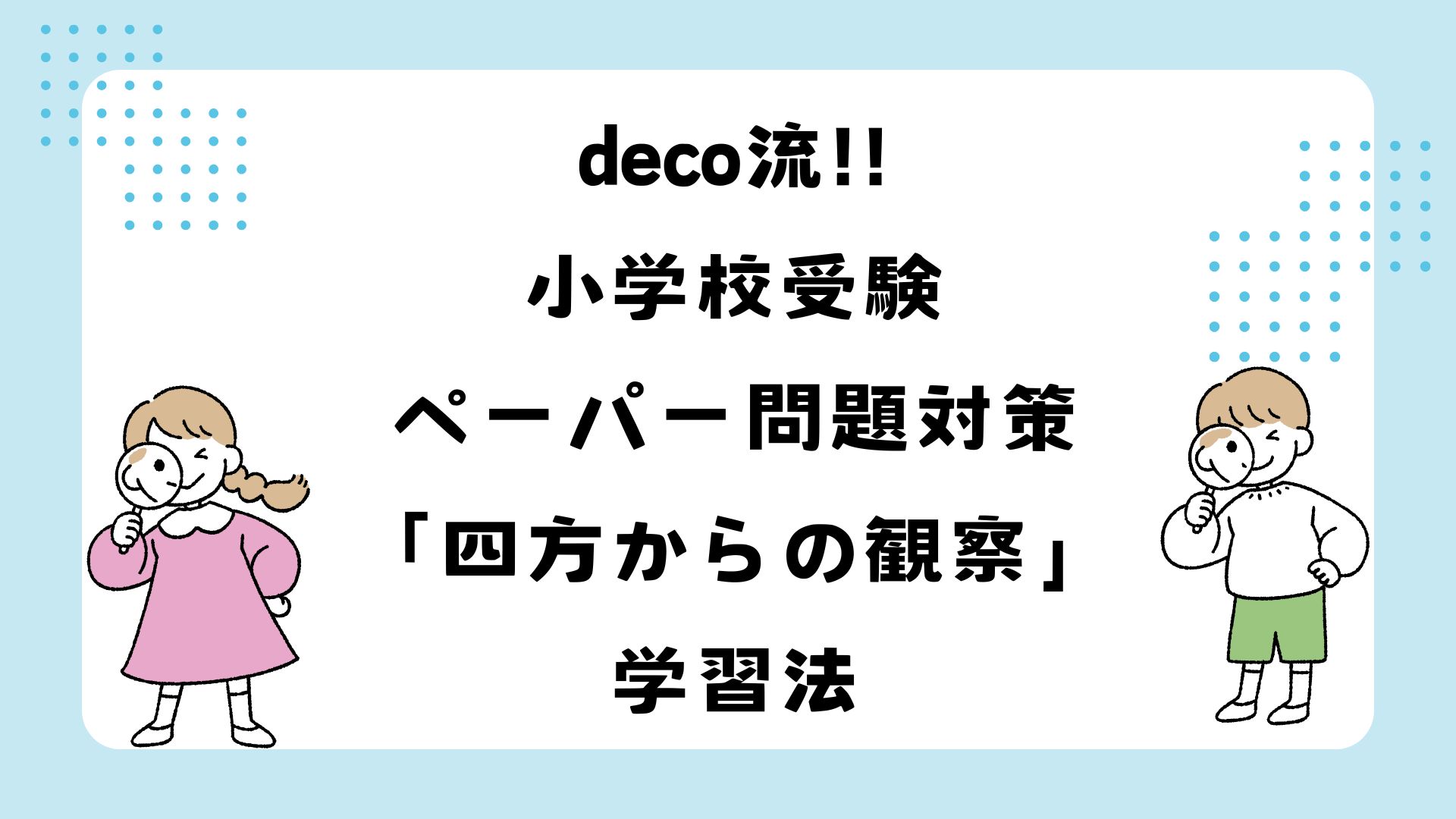
この記事にはアフィリエイト広告が含まれます
小学校受験の定番「四方観察」とは?
小学校受験のペーパー問題で
必ずといっていいほど出題されるのが
「四方からの観察(四方観察)」です。
机の上に積み木や物が置かれ
「前・後・左・右」から見たときの形を答える問題。
空間認識力・想像力・論理的思考のすべてを試される
超重要分野です。

2択までは絞れたのに間違ってしまう…
そんな惜しいミスに悩むご家庭も多いはず。
ここでは
2児ワーママdeco流・家庭学習でできる四方観察の克服法
を紹介します。
【ステップ1】前から見たら?一番やさしい基本問題
まずは「前から見た図」からスタートしましょう。
お子さまがプリントを見ている方向=前方向です。
そのまま見た形を選ぶだけなので、最初の導入にぴったりです。
☑次のステップに進むために意識したいこと:左右の認識力

うちの子はお箸の手が右と理解しているから大丈夫!
そう思っていませんか?
実は、相手の立場になったときの左右を
理解できていないケースが多いのです。
親御さんが向かい合って

お母さんの右手はどっち?
と質問してみてください。
すぐに正解できたら次の段階へ進みましょう。
小学校受験の四方観察では、
左右の概念が完全に定着していることが前提になります。
早めに問題集などで慣らしておくのがおすすめです。
【ステップ2】左右から見たら?立体をイメージする力を育てよう
前方向に慣れたら、次は「左右からの観察」。
ここからが本格的な思考力問題です。
🧠考え方のポイント
たとえば右側から見たとき、
まず「2段と3段の積み木が見える」まではOKだと思います。
次にこう問いかけてみましょう👇

右側に立って両手を前に伸ばしたとき、右手で触れるのはどっちの積み木かな?
お子様が「2段!」と答えられたら正解。
この「自分と相手の視点を切り替える力」こそ、四方観察の肝です。
解答欄を見るときも、「右手側に2段がある図」を選べばOKです。
この解き方ができるようになると四方観察ならどの位置からでも答えられるようになります
【ステップ3】後ろから見たら?反転の考え方でスピードアップ
「後ろからの観察」は、多くのお子さまがつまずくポイント。
ですが、考え方は左右から見た場合と同じです。
💡解き方のコツ
後ろ側に立った人の右手がどの積み木を触るか?を想像して解きましょう。
最初のうちは「右手で触れるものはどれ?」と毎回声かけをして、習慣化するのが効果的です。
慣れてきたら次の段階へ。
実は、「前」と「後」、「左」と「右」の答えは反転しています。
この法則を知っておくと、解答スピードがぐっと上がります。
🔍鏡のように考えると、後ろから見た図は「前からの図の反転」です。
鏡問題(鏡映像)の考え方を応用すると、理解がさらに深まります。
【ステップ4】おすすめ教材と家庭学習法
理解を定着させるには、繰り返しの演習が欠かせません。
deco家では、次の教材にお世話になりました。
📘おすすめ問題集
SmileKids「鏡映像・四方からの観察」
鏡・光・影など、関連単元をまとめて学べる良教材。
観察力+思考力を同時に鍛えられます。
ジュニアウォッチャー「四方からの観察 -積み木編-」
レベル別で問題を選べるので、苦手克服にも最適です。
【まとめ】四方観察を得意にする3ステップ
1.基本の前方向で左右の理解を定着
2.左右・後ろの観察で反転思考を身につける
3.問題演習でスピードと正確性を磨く
🔖関連ページ
あなたもWordPressでブログデビューしてみませんか?
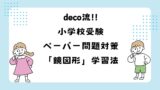
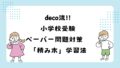
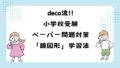
コメント