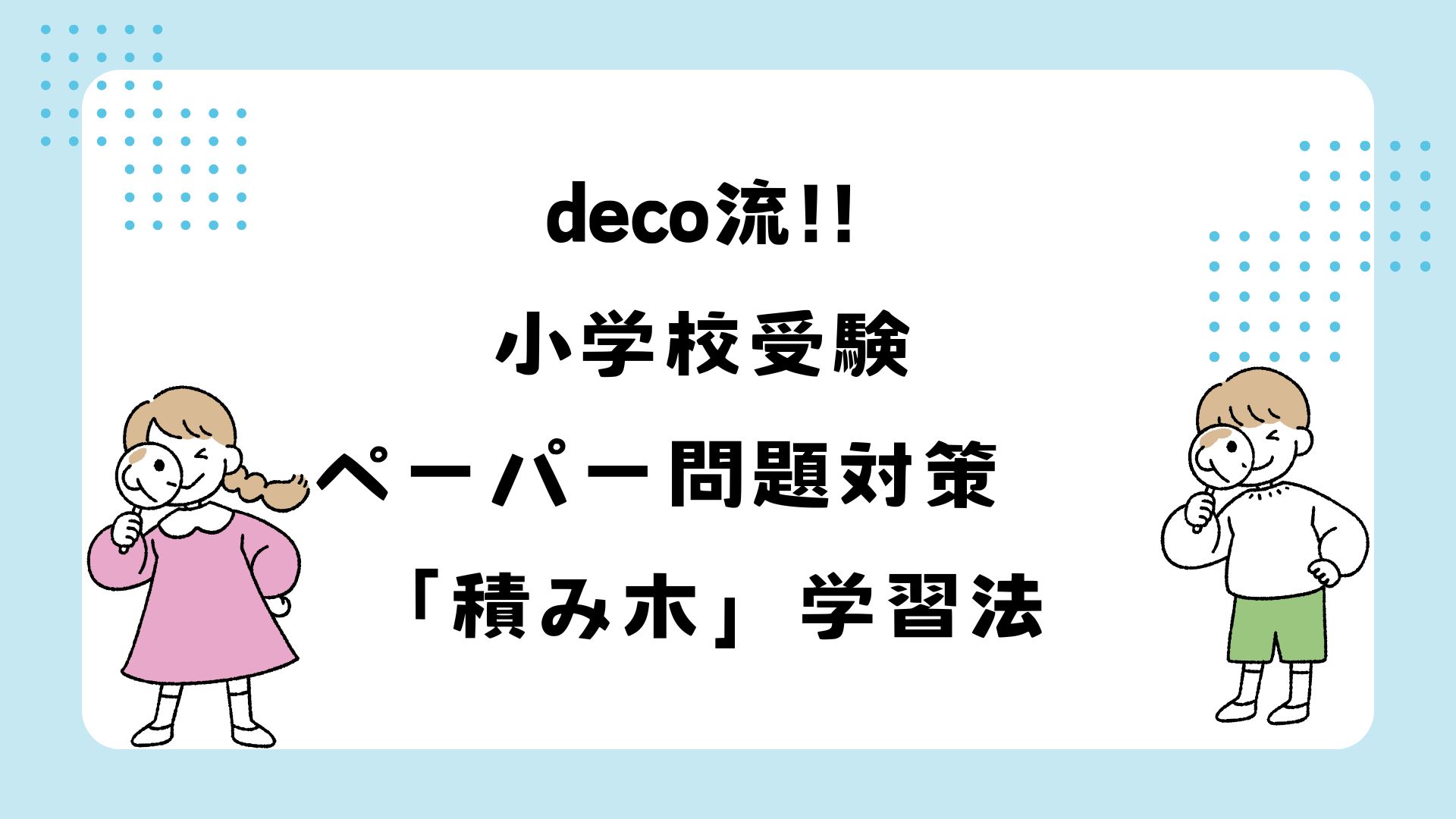
この記事にはアフィリエイト広告が含まれます
🧩 小学校受験で超頻出!「積み木」問題とは?
小学校受験と聞いて、まず思い浮かべるのが「積み木」の問題ではないでしょうか。
それほどまでに「積み木」は多くの学校で出題される、超定番かつ重要な分野です。
試験では、単純に積み木の数を数える基礎的な問題から始まり、
「四方からの観察」や「重ね図形」など、ほかの分野と組み合わされた複合問題も頻出します。
👉四方からの観察の家庭学習法はこちら
たとえば、テトリスやパズルのように条件がそろうと積み木が消えたり、
特定の方向から見たときの形を答えるような応用問題も登場します。
そのため、「四方からの観察は得意なのに、積み木がわからなくて正解できない…」
というケースも少なくありません。
「積み木」は、空間認識力・論理的思考力・集中力を総合的に試される分野。
この分野をしっかり理解しておくことで、ほかの図形問題にも強くなります。
🎯 「積み木」を苦手とする子が多い理由
積み木の問題でつまずくお子さんはとても多いです。
その最大の理由は、”頭の中で立体をイメージする力(空間認識力)”がまだ十分に育っていないからです。
平面上の図を見て、「この裏にも積み木があるのかな?」「見えない場所に何個あるんだろう?」と
想像するのは、幼児期の子どもにとってはとても難しいこと。
実際、ペーパーだけで説明してもピンとこないことがほとんどです。
「なんでこの積み木は見えないの?」「これって同じ形?」と混乱してしまい、
苦手意識が強くなるお子さんも少なくありません。
けれど安心してください。
この空間認識力はトレーニングで必ず伸ばせる力です。
「手で触って理解する」段階をしっかり踏むこと。
具体的には、実際の立方体積み木を使って「見えない積み木」を確かめながら遊ぶことで、
自然と「頭の中で形を組み立てる力」が育っていきます。
🧱 「積み木」克服の第一歩!おすすめ教材と使い方
積み木問題を得意にするための第一歩は、実物を使った体験学習です。
どんなに優秀なお子さんでも、最初から頭の中で立体を思い描くのは難しいもの。
まずは、手を動かして“目で見て、触って”理解することが大切です。
おすすめの教材は、ずばり「立方体の積み木」。
市販の立方体ブロックや、受験用の積み木教材を1セット用意しておきましょう。
最初のうちは、保護者の方が問題図と同じ形を積み木で組み立てて見せてあげます。
そしてお子さんには、実際に触りながらバラしてもらうのがおすすめです。
バラしていく過程で、
「見えていない部分にも積み木があるんだ!」
という感覚が自然と身につきます。その次のステップでは、お子さん自身に問題図を見せて、
「同じ形を作ってみよう」と声をかけてみてください。
はじめは時間がかかっても大丈夫。
焦らせず、静かに見守ることが何より大切です。
お子さんが自分のペースで形を作ることで、空間のイメージが定着していきます。
できるようになってきたら、
「下には何段あるかな?」「この奥には積み木が隠れている?」と
質問しながら確認してみましょう。
遊びながら積み木の構造を考える力が育ち、
徐々にペーパー問題でもスムーズに答えられるようになります。
🧮 「積み木」の数え方と練習ステップ
積み木問題の次の壁は、「隠れた積み木を正確に数えられない」こと。
これは多くのお子さんがつまずくポイントです。
積み木を数えるときに大切なのは、
1つずつ数えるのではなく、「塊で認識する」ことです。
たとえば、見えている積み木を数えたあとに、
「この下にも同じ形がもう1段ある」とイメージできるようになると、
数え間違いがぐっと減ります。
🪜 練習のステップ
① 親が作って、子どもが分解する
まずは保護者が問題図と同じ形を立方体積み木で作り、
お子さんに「バラして数えてみよう」と伝えましょう。積み木を崩すときに、「この下にもあった!」「ここに3段もある!」と
気づく体験を通して、見えない積み木を意識する力が身につきます。
② 子どもが自分で組み立てる
次に、お子さんが問題を見ながら同じ形を作る練習へ。
最初は時間がかかっても構いません。
親が急かしたり、答えを誘導したりせず、見守る姿勢を大切にしましょう。
③ 「塊」で数える練習へ
ある程度形をつくれるようになったら、
今度は「この縦の列でいくつある?」「横は何段かな?」と
縦・横の塊で数える習慣を身につけていきます。
このとき、「足し算の式」は書かなくても大丈夫です。
「手前に5個」「奥に3段の積み木が2組」「その横に2段が1つ」
といったように、言葉で整理しながら数える練習を繰り返すと効果的です。
💡 deco流アドバイス
・「積み木=楽しいもの」と感じてもらうことが一番大切!
・最初のうちは親が隣で「今ここ数えるね」「次はここを見てみよう」と声をかけてOK
・子どもが慣れてきたら、声かけを減らし“自分ルール”で数えさせる
家庭での積み木遊びを通して、
お子さんは“図形を立体的にとらえる力”を自然に伸ばしていきます。
🎓 家庭学習で積み木を得意にする!おすすめ教材と活用法
「積み木を苦手にさせたくない」「家庭でもしっかり対策したい」
そんなご家庭におすすめなのが、通信教材や専用の受験対策教材です。
実際、私deco家でも試行錯誤の末に取り入れた教材が大正解でした。
中でもおすすめなのが、こぐま会の家庭学習教材です。
こぐま会の教材は、単なるプリント学習ではなく、
実際に手を動かしながら立体の理解を深める工夫がたくさん。
特に「積み木」「重ね図形」「四方からの観察」などの
図形・空間認識系分野の基礎をしっかり固められる内容になっています。
「どんな教材を選べばいいかわからない…」という親御さんにも安心で、
月ごとに届くテーマ別の課題で、無理なく続けられる設計です。
基礎~応用まで徹底的に積み木の問題演習をしたい方は、
ジュニアウォッチャー 積み木やひとりでとっくん65 つみきのかずがオススメ。
お子さまのレベルに合わせて問題を選ぶことができるのがいいところです。
💻 タブレット教材で楽しく学ぶのもアリ!
「机に向かうのがまだ難しい」というお子さんには、
タブレット学習も効果的です。
たとえばスマイルゼミなどの幼児向け講座では、
立体図形や形合わせのアニメーション教材があり、
遊びながら積み木感覚を養うことができます。
音声付きで「見て・聞いて・触れる」学びができるので、
積み木問題の基礎になる空間イメージ力を自然に育てられます。

🧩 deco流まとめ
積み木問題を得意にするための近道は、
① 手で触って体感する👉立方体積み木
② 自分で組み立ててイメージする👉立方体積み木
③ 楽しく継続する👉幼児コース
④ 問題演習👉ジュニアウォッチャー 積み木・ひとりでとっくん65 つみきのかず
この4つに尽きます。
積み木は、小学校受験だけでなく、入学後の算数・図形分野の土台にもなります。
遊び感覚で学びながら、「考えることが楽しい!」と感じられるような環境づくりをしてあげましょう🌷
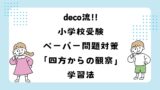
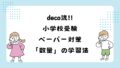
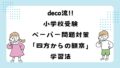
コメント