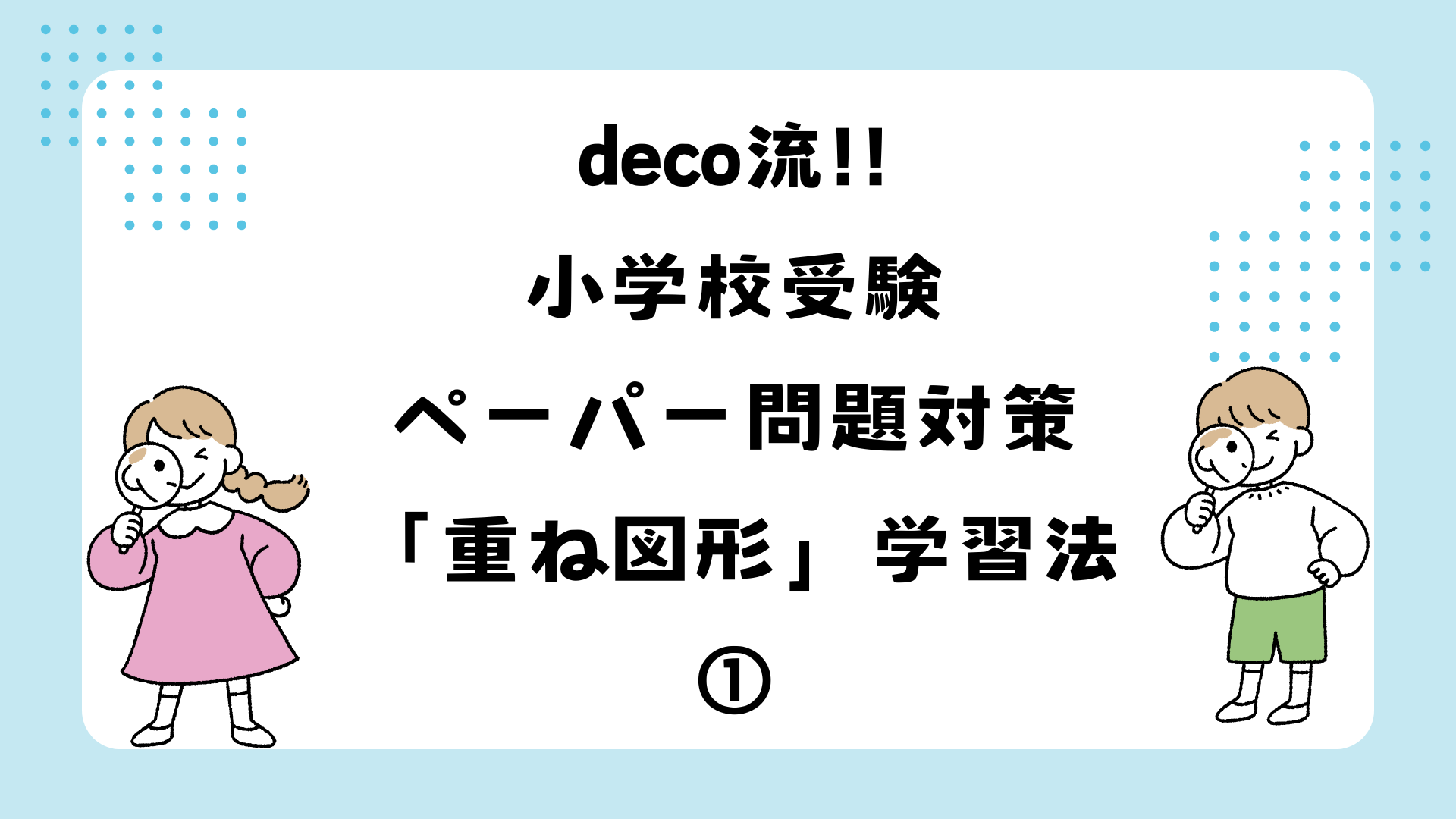
この記事にはアフィリエイト広告が含まれます
小学校受験のペーパー問題で、多くのお子さまがつまずく「重ね図形」。
でも、コツを押さえれば 得点源に変えられる分野 です。
この記事では、働くママでも家庭で無理なくできる「重ね図形」の学習法を、
実践ステップやおすすめ教材とともにわかりやすく解説します。
📌 この記事でわかること
- 小学校受験で「重ね図形」が得点差につながる理由
- 家庭でできる「重ね図形」体験法
- 具体的な解き方ステップ(丁寧に写すコツ)
- おすすめ教材・知育グッズ
- 学習を長続きさせるコツ
小学校受験で差がつく「重ね図形」とは?
小学校受験の図形・空間認識問題は、主に以下の3分野があります。
- 回転図形
- 重ね図形
- 鏡図形(反転)
この中でも 「重ね図形」 は、図形を正確にイメージする力と観察力が問われ、
特に難関校では 複雑な複数枚の図形を組み合わせる問題 が出題されます。
✅ 言語や常識問題は準備すれば差がつきにくいですが、
図形分野は得手不得手がはっきり出るので、合否を左右する重要ポイントです。
重ね図形が難しい理由
家庭では「重ねる体験」が少ないのが原因です。
- 日常生活で「何かを重ねて透かして見る」経験はほぼない
- 出題形式は透明フィルムや紙の上に図形を重ねる場合が多い
そのため、頭の中だけで重ねる練習ができず、イメージがつかみにくいのです。
家庭でできる!重ね図形の練習法
💡おすすめ① 透明素材を使って体験
- プラバンやクリアファイルに図形を描き、重ねる
- 色の違う図形を重ねて新しい形を観察
- 最初は家庭にあるものでもOK!
💡おすすめ② おもちゃ教材で楽しく学ぶ
- 「七田式 重ね図形パズル」など、遊びながら学べる知育玩具
- 重ね・回転・反転の3大分野を自然に体験できる
- ゲーム感覚で「苦手」を「楽しい」に変えられる
実践!重ね図形の解き方ステップ
重ね図形STEP① 重ねる図形を決める
- どちらの図形を動かすか決定
- 例:左の図を右に重ねる
STEP② 色のあるマスを丁寧に写す
- 感覚で選ばず、1マスずつ正確に写す
- 左の図→右の図へ段階的に移す
STEP③ 選択肢と慎重に見比べる
- 線やマスの位置まで丁寧に確認
- 「なんとなく」ではなく正確さが得点源
📘おすすめ教材
得点源にするコツ
重ね図形を得意にするカギは、ひらめきではなく“丁寧さ”と“忍耐力”。
重ね図形を苦手とするお子さまの多くは、
この「コツコツ作業」を面倒に感じてしまいます。
でも、実はこの地道な積み重ねこそが、
図形センスを育てる最大の近道なんです。
点図形や塗り絵のような単純作業を、
1日1枚でもいいので続けていく ことを意識してみてください。
それが積み重なると、
自然と図形を見る目と集中力が鍛えられます。
次のステップ!「折り重ね図形」に挑戦
重ね図形に慣れてきたら、次はもう一段ステップアップして
「折り重ね図形」に挑戦してみましょう。
折り重ね図形は、単に図形を重ねるだけでなく、
“折り返して反転させる” という要素が加わります。
つまり「重ね」と「鏡映し(反転)」の考え方が一体になった応用問題。
難関校ではこの形式が非常によく出題されます。
最初は少し難しく感じるかもしれませんが、
重ね図形の考え方が身についていれば大丈夫。
基本の「細分化して丁寧に写す」ステップをそのまま応用すれば、
折り重ね問題もきっとスムーズに解けるようになります。
🔗 詳しくはこちら
【小学校受験】折り重ね図形の解き方と家庭学習法【例題付き】
家庭学習を長続きさせるコツ
小学校受験の準備は、長いマラソンのようなもの。
一気に頑張るよりも、短時間でも毎日コツコツ続けることが大切です。
特に重ね図形や折り重ね図形のような図形分野は、
感覚を定着させるまでに時間がかかる分野。
「今日はここまでできたね!」と小さな達成を褒めてあげることで、
お子さまのやる気がぐんとアップします✨
📘続けやすいおすすめ教材
こぐま会『ひとりでとっくん47 重ね図形』
→ 基礎〜応用まで段階的に学べる人気教材。
七田式 重ね図形パズル
→ 遊びながら「重ね・反転・回転」を体験できる知育玩具。
ジュニアウォッチャー 重ね図形
→ 実践問題で入試レベルまでしっかりカバー。
どの教材も、子どもの「できた!」を積み重ねられる設計になっています。
無理せず楽しみながら進めることが一番のコツです💮
まとめ:「重ね図形」は“丁寧さ”と“体験”がカギ
小学校受験の図形問題は、一見難しそうに見えても
正しい順序で練習すれば、必ず得点源に変わります。
重ね図形で大切なのは、
🌸「感覚」よりも「丁寧な作業」
🌸「ひらめき」よりも「積み重ね」
そして何よりも、
🌸「楽しく体験しながら続ける」ことです。
お子さまの「わかった!」が増えるたびに、
確実に自信がついていきます。
焦らず、日々の学習を大切に。
重ね図形を制すれば、受験のペーパー対策がぐんと楽になります✨
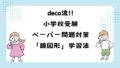
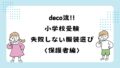
コメント